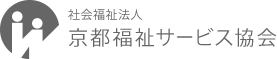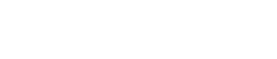事業所ニュース
名月やあの世この世をへだてなく
高野事務所のご利用者Mさんの俳句を今月もご紹介出来ることに喜びを感じています。筆者の記憶が正しければ、7月から連続して京都新聞の俳壇に採用されているかと思います。Mさんの俳句への情熱の高さはいかばかりと思わずにはおれません。今回は「中秋の名月」を詠まれました。
秋の澄んだ夜空に煌々と照る月の光は「陰」の美しさがあり、その直線的で青白い光の妖しさに、人はふと心を奪われてしまうことがあります。そして、日々正確にその形を変えて現れる月の中でも、暗闇を茫々と照らす満月の輝きを眺めていますと、そのまま宇宙の彼方に吸い込まれて行くような錯覚にも陥ります。Mさんが「あの世とこの世の境が失せてきた」と表現されたのはそんな感覚なのかも知れません。
さて月と言えば、詩集「月に吠える」で詩壇にデビューした「萩原朔太郎(1886年~1942年)」を挙げないとならないでしょう。彼のエッセイ「月と詩情」の一部をご紹介しましょう。「月とその月光が、何故にかくも昔から、多くの詩人の心を傷心せしめたらうか。思ふにその理由は、月光の青白い光が、メランコリツクな詩的な情緒を、人の心に強く呼び起させることにもよる。だがもつと本質的な原因は、それが広茫極みなき天の穹窿(きゅうりゅう)で、無限の遠方にあるといふことである。なぜならすべて遠方にある者は、人の心に一種の憧憬と郷愁を呼び起し、それ自らが抒情詩のセンチメントになるからである。」
このように詩人にとっての月へのあこがれは昔から尽きないようですが、翻って現代においては、24時間眠らぬ社会が続いており、人工照明が至る所で暗闇を照らし、人が月の光を愛でる機会は減っているのでしょう。晩秋の夜、たまには月や星を眺めるのも乙なものではないでしょうか。
最後にひとつ、月夜にちなんだ歌をご紹介します。作詞は、萩原朔太郎と同時代に活躍した「中原中也(1907年~1937年)」その詩に曲を付けて歌ったのは、1969年に「別れのサンバ」でデビューしたシンガーソングライターでギタリストの「長谷川きよし」題名は「月夜の浜辺」です。内容はちょっとシュールな感じもしますが、歌をじっくり聴いていただくと、自分にとって「大切なもの」は何かを考えるきっかけになるかと思います。↓をクリックすると試聴できます。
https://www.youtube.com/watch?v=9RDR8s2Yuf4
月夜の晩に、ボタンが一つ
波打際(なみうちぎわ)に、 落ちていた。
それを拾って、役立てようと 僕は思ったわけでもないが なぜだかそれを捨てるに忍びず
僕はそれを、袂(たもと)に入れた。
月夜の晩に、ボタンが一つ
波打際に、落ちていた。
それを拾って、役立てようと 僕は思ったわけでもないが
月に向ってそれは抛(ほう)れず 浪に向ってそれは抛れず 僕はそれを、袂に入れた。
月夜の晩に、拾ったボタンは
指先に沁(し)み、心に沁みた。
月夜の晩に、拾ったボタンは
どうしてそれが、捨てられようか?
Mさん、今年も1年間数々の俳句をありがとうございました。また、高野事務所のこのブログを読んで下さった方々にも感謝します。2024年が良い年になるように皆さんと共に祈りたいと思います。前回までの作品をご覧になりたい方は↓をクリックして下さい。 https://www.kyoto-fukushi.org/office/news/12607/